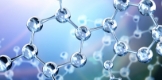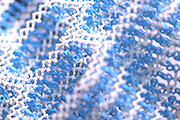2050年に向けた電気自動車の「動く蓄電池」としての役割の変化
当社の片岡良介らが東京大学生産技術研究所エネルギーシステムインテグレーション社会連携研究部門と共同で行った研究が Energy に掲載されました。
脱炭素社会の実現に向けて、再生可能エネルギーとバッテリー電気自動車(BEV)の協調が注目されています。発電量の変動が大きいという再エネのデメリットに対し、BEVが「動く蓄電池」として柔軟に充電・蓄電・放電することで、再エネの効率的な活用につながると期待されています。一方で、排出削減目標と整合するエネルギーシステムには、再エネの他、原子力や合成燃料等の多様な技術の組合せが予想されるため、BEVの果たす役割の将来性は不明瞭でした。
本研究では、2050年に向けた長期的なエネルギー計画モデルと詳細な電力モデルを用いて、日本の多様な脱炭素シナリオにおけるBEVの役割を評価しました。その結果、脱炭素に向けてBEVと太陽光発電の協調が一貫して重要であり、また、火力発電の効率的運用と合成燃料の消費削減を通じてBEVの経済的な貢献が拡大する結果が得られました。この成果は、BEVが単なる移動手段を超え、エネルギーシステムの環境性と経済性に貢献する重要な技術であることを示しており、太陽光発電の活用と燃料コストに課題を抱える日本や他の国々に有益な示唆を与えます。
タイトル: Changing Role of Battery Electric Vehicle Charging Strategies in Decarbonizing Japanese Power Systems
著者: Kataoka, R., Ogimoto, K., Iwafune, Y., Nishi, T.
掲載誌: Energy
掲載日: 2025年5月4日
https://doi.org/10.1016/j.energy.2025.136413