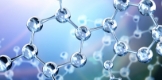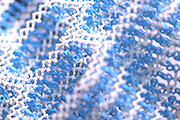人を対象とする研究に関する取組み
人間の行動、意識、感情、印象、快適さ、疲労等を科学的に理解することは、将来の社会課題解決に向けた技術開発において重要であり、当所ではその手段として人を対象とする研究を実施しております。当所では、「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」(令和3年文部科学省、厚生労働省、経済産業省告示第1号(令和4年3月10日一部改正))に定められた事項の他、必要な事項を定めた社内規程を制定し、研究倫理審査委員会*1を設置して、人を対象とする研究の適正な実施のための取組みを行っています。当所では、臨床研究や治験等は実施しておらず、侵襲有りの実験は行いませんが、軽微な侵襲の実験に対しても、科学上の目的を達成できる範囲で事故等の発生を防止すべく、審査を通して十分な対策を講じ、実施しております。
また、人を対象とする研究に携わる者 (研究者、技術者、研究倫理審査委員会委員、研究倫理審査事務局、等)には、人を対象とする研究に関する年1回以上の教育受講を義務付けており、研究対象者の人権保護をはじめ、法令順守、そしてコンプライアンスに関する意識・知識の向上を図っています。
*1 研究倫理審査委員会報告システム(厚生労働省)に登録されています。
動物を扱う実験に関する取組み
人間の健康・福祉や環境の保全と再生などの課題解決に向け、生命活動を科学的に理解することは重要であり、そのために不可欠な手段である場合のみ、当所は動物実験について検討を行います。当所では、「動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)」をはじめとする各法令、基準や基本指針、ガイドラインに基づき、社内規程を制定し、動物実験倫理審査委員会を設置して、動物実験を適正に実施するための取組みを行っています。なお、社内規程では、法令で規定されている哺乳類、鳥類、爬虫類に加え、魚類、両生類、無脊椎動物も適用範囲としています。
動物実験倫理審査委員会は、4Rの原則*2の観点で動物実験が計画されているか等について厳正な審査を行います。なお、当所は、現状、法令で規定されている哺乳類、鳥類、爬虫類の飼養施設、実験施設を保有しておらず、当所の敷地内で当該動物を対象とした実験を実施することはありません。
動物実験に携わる者(研究者、技術者、動物実験倫理審査委員会委員、動物実験倫理審査事務局、等)には、動物実験、及び実験動物に関する年1回以上の教育受講を義務付けています。また、年1回以上の内部点検の機会を持ち、動物実験等が法令や所内規程等に即して実施されていることを確認しています。
*2 4Rの原則
・Replacement(代替法の利用):動物を用いなくても可能な方法についての検討
・Reduction(実験動物数の削減):できる限り供される動物の数を少なくすることについての検討
・Refinement(苦痛の軽減):できる限り供される動物の苦痛を軽減する方法についての検討
・Responsibility(研究者及び実験者の責任):実験の意義、必要性及び予見性に関する十分な説明